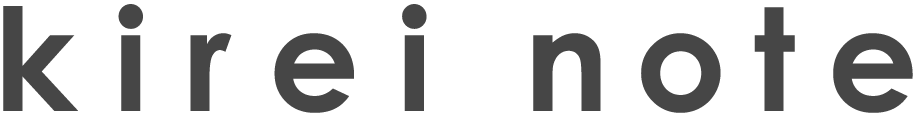<山脇源平商店>ふわりと温もる近江真綿の魅力と歴史 #巡る滋賀
滋賀県の最大の魅力といえば、滋賀県の代名詞でもある日本最大の湖・琵琶湖。その他、国宝の「彦根城」やユネスコ世界文化遺産の「比叡山延暦寺」など一度は訪れたい観光スポットもまた有名です。
でも、それだけではありません。有名観光スポット以外に焦点を当て深掘りすると、まだまだ知られていない注目ポイントがたくさん! それを知らないなんてもったいない…!
この連載では、「現地の方がおすすめしたいスポットやお店、それをつくるヒトの魅力をていねいに取材し、お届けする滋賀の観光ガイド“巡る滋賀”」の情報を発信していきます。
滋賀県への旅のきっかけやガイドブックとなりますように…そんな思いを込めて滋賀県の新たな魅力をお伝えします。
繭から生まれる肌へのやさしさ。受け継がれて300年、彦根藩お墨付き「山脇源平商店」の真綿とは?
滋賀県の伝統的工芸品に認定されている「近江真綿(おうみまわた)」。古くからこの真綿製造の盛んな地域として知られるのが、米原市岩脇(いをぎ)地区です。最盛期には地域の7割がこの真綿製造に携わっていたものの、現在ではたった1軒のみ。真綿の良さや魅力、そしてさらなる可能性について、この場所で変わらない伝統を受け継いでいる老舗「山脇源平商店」代表の山脇和博さんにお話を伺いました。
真綿ってどんなもの?
みなさん、「真綿(まわた)」をご存知ですか?“綿”とついていますが、コットン(木綿)のことではありません。真綿とはカイコの繭を煮て引き伸ばしたもののことで、シルク、すなわち絹製品のひとつなのです。

およそ2000年ほど前に日本へ入ってきたといわれる絹と養蚕の技術。日本の主要な産業であった時期も少なくありません。1500年代後半に綿花(めんか、植物としての「ワタ」)が日本でも一般化するようになると、後年、その名前に変化が。従来より“綿”と呼んでいた絹製品に加え、木綿のことも“綿”というようになったため、江戸時代中期の頃からは、“真の綿(ほんとうの綿との意味)”と書いて「真綿」との呼び名が定着するようになったのだそうです。

この真綿が特に活躍するのが布団です。真綿を中綿に使った「真綿布団」は人の身体との高い親和性が魅力で、シルクの滑らかな肌触りと保湿力に加え、その軽さと、寝返りを打ってもついてくるほどのフィット感で体をやわらかく包んでくれます。
繭からとれる細かい繊維群が中綿に空気の層を多くつくることで、高い保温性を有しながらも、シルクの吸放湿性の高さから蒸れにくさも併せ持つという優れものに。したがって夏は涼しく、冬は暖かく。オールシーズン快適に眠れるのが、この真綿布団なのです。綿ほこりが出にくく、抗菌・抗酸化作用、消臭作用があるのも嬉しいポイントですね。


熟練の技が冴えわたる、真綿づくり
「江戸時代の文書の中に『糸取り3日、真綿づくりは1年かかる』と残されとった。こう言うと作る人には『もっと難しいんや』と叱られるかもしれないが、それぐらい簡単じゃないということ」と話すのは、山脇源平商店・9代目の山脇和博さん。

のちに屋号となる源兵衛(げんべえ)さんが商売を始めたとされるのが1730年ごろ。まもなく創業300年を迎える山脇源平商店では、当時と変わらぬ製法で真綿の製造を行っています。

ここで主に作られるのは「角真綿(かくまわた)」。
まずは、“練り”という作業でカイコのつくる繭を柔らかくします。そしてその柔らかくなった繭を、水中で一つずつ丁寧に引き伸ばし、四角い木枠に4枚ずつ重ねていくのが“真綿かけ”の工程。厚さを均一にすることもさることながら、山から流れてくる冷たい水に浸けながらの手作業であることが何より大変なこと。最後にこれらを枠から外して乾燥させれば「角真綿」の完成です。


この日も3名の方が真綿かけに励んでいらっしゃいました。初めは丸い繭を手でゆっくり広げていきます。徐々に引き伸ばしながら、四隅の切り込みにひっかけるようにして薄くしていくのですが、破れそうで破れないのが熟練の技術。うしろが透けて見えるほどの均一な薄さは、まさにプロの手仕事。みなさんの指先の技術にはほれぼれするばかりでした。



そして、完成した角真綿を真綿布団にするには、ここからさらに“手引き”という工程が必要です。こちらも熟練の職人のなせる業。風が吹けばクシャっとなってしまいそうなほどの薄さ。2人がかりで息を合わせ、ムラなく均一に引き延ばし、何百回と重ね合わせます。


布団の中綿は1枚あたり1~1.5kgほど、また1kgの中綿を作るのに必要な繭はなんと3000個!「1日真綿かけの作業をしても、1人だいたい400gくらい」と山脇さんはいいますから、真綿かけは1人が1日で約1200個の繭を引き延ばしている計算に。そして3人がかりで1日作業したとしても、それでやっと布団1枚分くらいにしかならないということなのです。
ごく微量ずつ、絶妙な力加減の手作業を繰り返し積み重ね、ようやく真綿布団の中綿は出来上がっています。
岩脇の伝統を守り、真綿づくりを続けるための取り組みとは?気になる続きはこちら
ディープな滋賀の魅力に出会える! 人気連載「巡る滋賀×キレイノート」の他記事は#巡る滋賀からご覧いただけます!
編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。
この著者の記事一覧へ