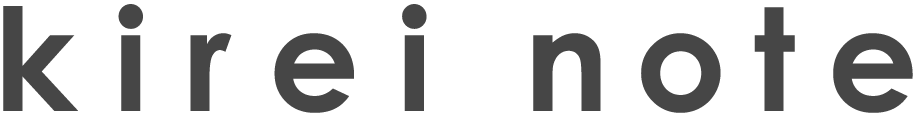2021.06.17
ダルダルの季節に「ピーマン」
ピーマンと肉団子の黒酢あん
仕事を休むほどではないけど、体がだるい、気持ちがスッキリしない、“なんとなくの不調”ってありますよね。
それ実は、季節や気候の変化が影響しているのかも。「季節の症状の改善には季節の食材が効果的」という東洋医学の知恵に基づき、旬をおいしくとり入れた献立=食養膳をお届けします。カラダとココロをセルフメンテナンスしていきましょう!
6月後期のカラダとココロ
1年で最も昼が長く夜が短い夏至(2021年は6月21日)の時期。高温多湿な梅雨の季節は胃腸の機能が低下し、食欲不振が起こりやすくなります。
東洋医学で、梅雨は「湿邪(しつじゃ=病原となる湿気)」が多くなる季節といわれています。また、根幹である考え方「五行(ごぎょう)」では、心身に対する役割や機能を肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・ 腎(じん)の5つに分類し、「五臓(ごぞう)」と呼んでいます(※現代医学の臓器を表すものではありません)。その中で、主に栄養や水分の消化吸収機能を司っているのが「脾」。「脾は燥を喜び、湿を悪む」という性質があるため、湿邪の多い梅雨は、脾の機能が低下しやすくなるのです。
もともと胃腸が弱く栄養の消化吸収能力が衰えている「脾虚(ひきょ)タイプ」は、空腹感がない、食べても味がしない、少量しか食べられない、食べると腹が張る、疲れやすいという症状が。一方、不摂生な食生活の影響で体内に湿が生じている、湿度の高さにより湿邪が脾胃に侵入している「湿困脾胃(しつこんひい)タイプ」は、吐き気、胃のつかえ、消化不良、体が重だるい、などの症状があります。
暑い時期は体表面に熱が集まって、お腹は冷えやすくなります。食欲がないからといって、果物や生野菜、麺類、冷たいジュースやゼリーなど、口あたりのよいものばかり食べていると、胃腸が冷えて脾の動きが弱ってしまうことに。本格的な夏を迎えたときに、夏バテの症状が出やすくなります。暑い時期ほど火が通ったメニューを中心に食事を摂ることが、これからの季節を元気にすごす秘訣です。
汗を上手にかいて代謝機能を上げ、汗腺をつまらないようにしておくことが、これからの季節に冷え性を起こさないことにもつながります。
この季節になるべく避けたいこと
胃腸を冷やすものや消化の悪いもの(生のもの、冷たいジュースなど)、冷房の使いすぎ、お腹を冷やすファッション

ダルダルの季節にピーマン
ビタミン豊富で栄養価の高い夏野菜・ピーマンは、胃腸を元気にして、食欲を増やす効果があるといわれています。また東洋医学で「食滞(しょくたい)」と呼ばれる消化不良を解消してくれる働きも。免疫力のアップや抗酸化作用があるカロテンも豊富で、油で調理すると吸収されやすくなります。そして実は、ワタと種の部分には血液をサラサラにする成分などが含まれていること、ご存知でしょうか。食感も楽しくおいしので、捨ててしまってはもったいない、ぜひつかってくださいね。
ピーマンを使った主食
ピーマンと肉団子の黒酢あん

材料(2人分)
- ピーマン 4個
- 豚ひき肉 200g
- ☆塩 少々
- こしょう 少々
- 酒 小さじ1
- しょうゆ 小さじ1
- オイスターソース 小さじ1
- 玉ねぎのみじん切り 100g
- おろししょうが 小さじ1
- パン粉 大さじ3
- 溶き卵 1/2個分
- 揚げ油 適宜
- ★砂糖 大さじ1/2
- しょうゆ 大さじ1
- 黒酢 大さじ1
- オイスターソース 小さじ1
- 水 大さじ2
- 水溶き片栗粉 適宜
- ごま油 少々
今回のテーマ食材「ピーマン」は油との相性が良く、丸ごと加熱すると中が蒸されてジューシーな仕上がりに。消化不良を解消して食欲増進の働きがあるといわれている黒酢、それから疲労回復効果のある豚肉をあわせた、梅雨時期の食欲不振解消にぴったりのメニューです。食欲をそそる黒酢の香りと甘辛味で、ごはんが進むこと間違いなし。油の効果でピーマンの苦みも抑えられ、種もヘタもおいしくいただけますよ。お酢は取りすぎると胃が熱くなるので、食欲がありすぎるとき、胃痛や咽痛など粘膜に炎症のあるときは気をつけましょう。


季節はめぐり、旬の食材も移り変わります。体は自ずから旬のものを欲しています。それは私たちが自然の一部である証拠。自分の内なる声に耳を傾け、自ら癒す。料理にはその力があります。
(献立担当) 鈴木聖子 Seiko Suzuki
料理研究家。大学で栄養学を習得し、卒業後は飲食店のスタッフトレーニングや商品開発の仕事に従事。その後オーストラリアへ渡り、レストランで働きながら食文化を学ぶ。帰国後はクッキングスクールに10年間勤務。2013年から「3さいからはじめる料理教室 KISSAKO」を主宰。季節の食材を使う料理レッスンのほか、企業向けのレシピ開発、ケータリング、加工食品販売なども手掛ける。頭の中は常においしいもののことでいっぱいな二児の母。
料理教室・料理研究家KISSAKO / instagram / facebook

そもそも日本は、海に囲まれている島国であり、湿気が高いため、脾の機能が低下しやすい環境です。食べると眠くなる、電車に揺られると眠くなる、争いごとは嫌い、面倒くさい、などは、日本人に多い特徴でもあり、脾が弱っている特徴です。
(カラダとココロ担当) 飛奈光重 Mitsue Tobina
漢方家。大学の薬学部在学中、医療ミスで祖母を亡くした経験から東洋医学と漢方の道へ。卒業後は漢方専門薬局に勤務し、数多くの漢方相談を受けることで臨床経験を積む。2019年「漢方専門 横浜梅桜堂薬局」を開業。婦人病、皮膚病、目の病気の研究に特に力を入れている。漢方歴25年、薬剤師と国際中医師の資格を持つ。
横浜梅桜堂薬局