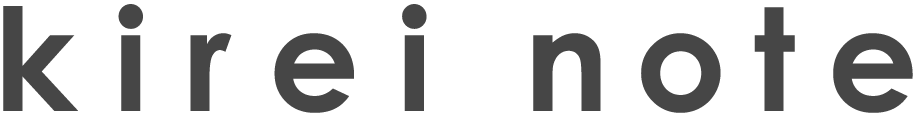2021.11.12
写真家・ヨシダナギの逃げの生き方
「結局は自己矛盾で生きている」
アフリカの少数民族に会いに行き、同じ格好になって心を通わせ、彼らの姿を写真に収める。そう聞くと、真っ先に写真家・ヨシダナギさんを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。この秋、2冊のエッセイを出版された彼女に、本のこと、写真のこと、旅のこと、人生のことをインタビュー。ミステリアスな彼女の人生観を少し覗いてみました。

心が通じた瞬間はいつも感動する
――ヨシダさんの代名詞といえば、アフリカなど世界各国の少数民族を撮影された作品です。幻想的で一枚の絵画のような印象を受けますが、撮影されるときはどんなことを考えていますか?
何も考えていないんです。彼らの構図とその表情を見ているだけで、私はとにかくシャッターを押すだけで。だいたい1時間以内に全てを終えるように、現場は時間との戦いです。私は逆光で撮影することが多いのですが、朝日や夕日などの時間帯は限られていますし、少数民族の方の集中力も続かない。だから細かに構図を決めたら、撮影自体は1カット15分~20分くらいでしょうか。
――でも、複数人を同じポーズで止めておくことは大変ですよね。しかも、言語も文化も違うお相手です。
相手がプロではないということは念頭に置くようにはしています。ただ、自分がすごくかっこいいと思っていた人たちなので、勝手に世に送り出したくなるというか。だんだんマネージャーのような気持ちになってきて(笑)。どの民族も最初は照れてモジモジしたりするんですけど、あるタイミングで突然全員がプロの顔に変わるときがあるんです。私が何も言っていないのに! その瞬間、「あ、うちの子が旅立った」という感覚になって。「心が通じたんだ」「同じ方向を向いてくれたんだな」と、すごく感動する瞬間ですね。

――その想いが、唯一無二の表現に繋がるんですね。写真家としてこうありたいなど、この先を考えることは?
最初の頃は、写真は旅の延長線にあるもので、私は作品に責任感を持っていなかったんです。でも、それがだんだん仕事になってくると、撮影期間が短いうえに求められるものが多すぎて、撮影が決まっただけで帯状疱疹が出ることもあって。私、ストレスや縛られることがダメで、基本的に働くことに向いていないんだと思うんです(笑)。
写真家という職業も、辞められるのだったらいつでも辞めます。でも、これまで撮影した少数民族のみなさんが、肩書きのなかった私を世に出してくれた。だから、写真家を続けているのは彼らに対する恩返しですね。彼らの姿をメディアで伝え、一人でも多くの人にかっこよさを知ってもらいたい。それをやり切るまでは続けると思います。
――もしもの話ですが、何も制限がなければ撮影したいものはありますか?
正直なところ、求められるものがなければ撮影したいとは思わなくて(笑)。写真を撮ること自体、趣味でもなければ好きでもない。彼ら(少数民族)に会いに行くことはもちろん好きなのでこれからも会いに行きますけど、撮影はしなくてもいいのなら撮らないと思います。

――ちなみに、海外に少数民族を撮影されに行くときは、「旅」という感覚ですか?
撮影に行くことが決まった瞬間は「旅」ですね。でも、家を出た瞬間に「仕事」になって(笑)。空港に向かっているときから、なんだか楽しめないんですよ。どこに行くか決めるまでとか、どんな作品を撮るかを考えるときはすごく楽しんですが、いざ現実になるとプレッシャーがストレスになるタイプで。もし純粋に旅に行けるのなら、撮影も何もなく行きたいですね。いつも行きたい場所はいくつか心にあって、その中からベストな場所を選んでいます。

次のフェーズに移ることが怖かった
――最近、被写体の幅が広がっていますよね。
3年前くらい前でしょうか。会いたかった少数 民族をひと通り撮影して、次の被写体を探さなきゃいけない段階に入ったとき、「何をどう美しいと感じて少数民族を撮影しているんだろう?」と、原点に戻る時期があったんです。そのうえで、今まで私が撮影してきた写真の美しさって何だろうとも考えて。これまでの作品を一度並べて考える時期を経て、その立ち姿の強さ、美しさが民族と通じるものがあるドラァグクイーンを被写体にして撮影したくなったんです。

――ご自身の作品を振り返るタイミングは、これまで何度もあったんですか?
いえ、そのときが初めてです。新しいものを撮らなきゃいけない、写真家として新しいフェーズにいかなきゃいけないというプレッシャーがあったのも大きいですね。正直、すっごく嫌でした(笑)。
私はアフリカ人が好きで純粋に追いかけていたら、後から写真家という肩書きがついてきました。だから、作品で人を喜ばせたいというモチベーションもなく、写真家になりたいと思って努力してきた人間でもない。だからこそ、新作や違う被写体を求められる期待に、「ありがたいけれどやめてほしい」と思っていました。でも、それに応えないと、少数民族のかっこよさを伝えられる場もなくなるのではと今度は怖くなって。それで新しい作品を撮ろうという、大人の考えをようやく持ちました(笑)。
――でも、”撮りたいと感じる人”という被写体の選び方には変わりないですよね?
はい。そこだけはブレちゃいけないと思っています。商業的な角度からも色々と提案はしていただいたんですが、なにせ写真家としての技術が私にはないんです。だからこそ、自分が興味を持てる人 、心から好きになれる人じゃないと、熱量が写真に入らないと思うんですよね。

――ドラァグクイーンの方々を撮影されて、新しい発見はありましたか?
「本当に人って自由でいいんだ」ということですね。他人からの意見なんてたいしたことない。かわいい、気持ち悪い、怖いとか、いろんなことをいわれることもあるけれど、自分を好きでいられる姿でいることが、その人にとって一番快適で幸せなことなんです。そういう姿を目の当たりにして、私が励まされました。

結局は自己矛盾で生きている
――この秋、2冊の書籍を出版されましたが、読み終わるとどちらも自由に生きていいんだという励ましをもらえる気がします。どんな方に読んでほしいですか?
実は、私にはこういう人に対して何かを発信したいという考えは元々ないんです。でも、出版社からお声がけいただき、特に『しれっと逃げ出すための本。』なのですが、作り終えてから「人に迷惑をかけたくない」と悩んでいる人がターゲットだったんだとわかりました、もう一冊『贔屓贔屓(ヒーキビーキ)』に関してですが、私の好きなことを誰が楽しんで読んでくれるんだろうって未だに疑問に思っています(笑)。
――『贔屓贔屓』も、好きに素直でいていいんだと励みになると思いますよ。どちらの本も、読み終わるとヨシダさんに人生相談できたかのような爽快感もあり、個人的には20〜30代の女性に響く本だとも思います。印象的だったのが「人生はあくまでも自分が主人公の物語」(『しれっと逃げだすための本。』より)というフレーズです。なぜこう思うように?
個展や作品集を発表するようになって、「人に迷惑をかけたくない」と悩む人から相談されることが多くなったんです。もちろん、人に迷惑をかけずに生きられたら美学なんでしょうけど、結果それは不可能じゃないですか。「私は人のために生きているわけではないし、人のために働いているわけじゃない」っていうことに気づいたとき、それが生きることの全てじゃないかなって思ったんです。
――ヨシダさんは、被写体となる方々には共通して立ち姿に生き様が現れると表現されていますよね。ご自身の生き様についてはどう感じていますか?
三分咲きですね。私、5歳の頃に「あなたは遅咲き」と占い師さんにいわれたことがあるんです。当時もショックでしたけど、17歳になってその意味をきちんと理解できたときに絶望を感じて。まだ咲かないのかって(笑)。でも、今では逆に楽しみになっていますよ、いつ咲けるのかなって。蕾が落ちる前に咲けたらいいですね。

――最後に、ヨシダさんが日常のなかで大切にしたいコトやモノは何でしょうか?
「考えすぎない」ということかな。アフリカに行ってから、よりそれが強くなった気がします。日本人は深く考えるところがすごくいいところではあると思うんです。でも、それが大きな足枷になるときもある。ありもしないことや予測だけで不安になることってあるじゃないですか。でもそれが自分で自分を追い込む要因になるし、だからこそ考えすぎないことも大事だと思います。
だって、人って追い込まれると、人相も貧相になってきませんか? 切羽詰まっていると、人が寄ってこなくなる。楽しそうにしている人の方がかわいらしく見えるし、困っていたら他人が拾ってくれたりもする。だから、あまり自分を追い詰めなくていいのではと思いますね。私自身、今回本を作ってみて改めて「自己矛盾で生きているな」と気づいたんです。完璧になんて生きられないし、どんなときでも“逃げる”っていう選択肢は持っていていいんじゃないかなと思います。
取材・文/野村紀沙枝
撮影/Paloma Benito
ヘアメイク/YOUCA

PROFILE
ヨシダナギ
1986年生まれ。独学で写真を学ぶ。世界中の少数民族やドラァグクイーンを撮影し、個展や作品集で発表する。昨年、3rd作品集となる『DRAG QUEEN -No Light, No Queen』を発売。エッセイも人気で、今年9月に『しれっと逃げ出すための本。』(YA 心の友だち)、10月に『贔屓贔屓(ヒーキビーキ)』(幻冬社単行本)を発売。11月30日から12月12日まで、九州では初となる写真展『DRAG QUEEN No Light, No Queen photo by nagi yoshida』を福岡市美術館で開催予定。


(左)『しれっと逃げ出すための本。』 ヨシダナギ 著 定価:本体1,430円(税込) 出版社:PHP研究所
(右)『贔屓贔屓(ヒーキビーキ)』 ヨシダナギ 著 定価:本体1,540円(税込) 出版社:幻冬舎
編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。
この著者の記事一覧へ