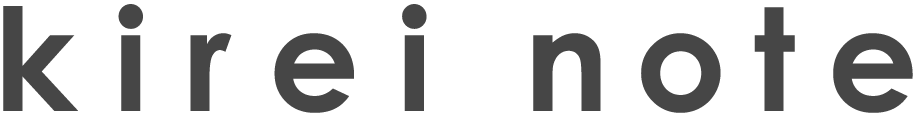2021.01.27
【おこもり美容ノートfromイタリア】内側からキレイを作る中国茶
イタリア 中国茶専門店「XINGCHA」
いいことだらけの中国茶を摂り入れよう
近年イタリアでは、和食人気に伴い日本茶の認知度が上がっています。
品質はさておき、緑茶やほうじ茶、玄米茶もスーパーで手に入るように。お茶の魅力にはまったイタリア人の中には、中国茶に注目する人も出てきました。

現在、またまたロックダウン中のミラノ。おうち時間を使って、ミラノの中国茶専門店「XINGCHA」から茶葉を取り寄せ、アドバイスを受けながら色々試してみることに。
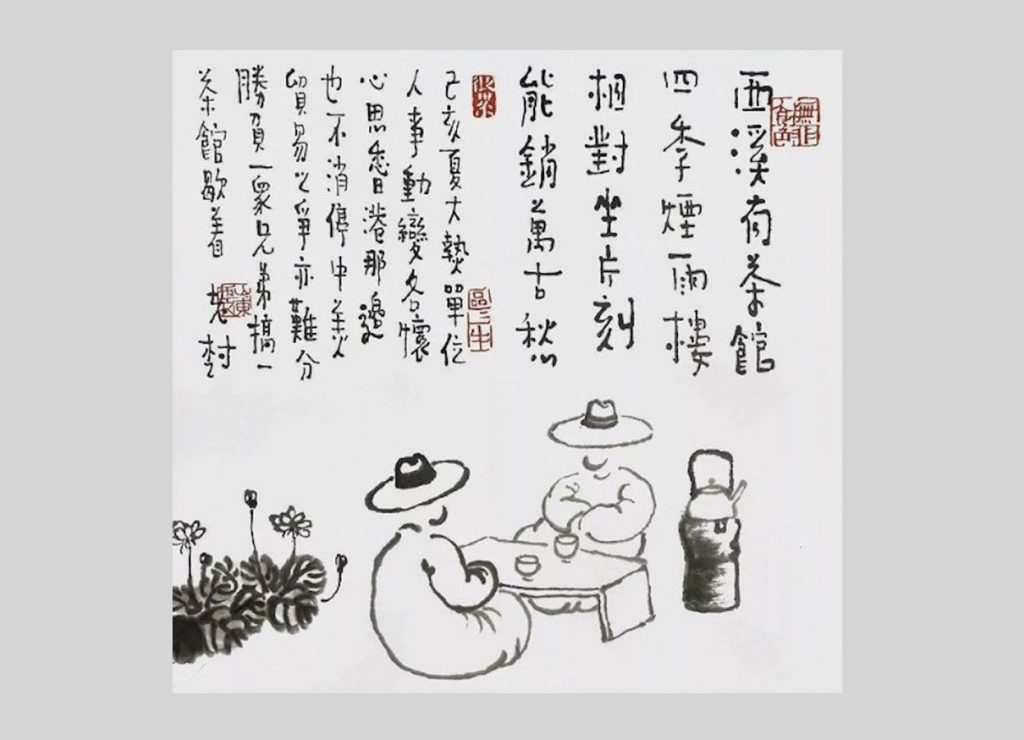
中国茶は、陰陽五行にも通じる奥深い世界。原料の「茶の木」は中国で五千年前から生息し、現在数千種の中国茶があるそうです。
数百年前まで薬として飲まれていたことからも、その効能はお墨付き。体質や体調、季節、料理などによって選ぶと、美味しいだけでなく健康にも嬉しい効果が期待できます。

茶葉の名前も素敵。三国志武将を彷彿とさせるものから麻雀の役のような名称もあり、中華浪漫の世界へと誘われます。
おうち時間を使って、中国茶の旅へと出発です!
覚えて損なし、中国茶の種類

まず知っておきたいのが、「冷茶」「温茶」の2分類。体を「冷やす(陰)」か「温める(陽)」か、という意味になります。発酵度が低いほど体を冷やし、高いほど温めます。
それでは、代表的な6大茶類の特徴、発酵度の低い順から簡単にご紹介していきます。
(※白茶・黒茶・青茶は種類により発酵度に差があります)
○緑茶

長い歴史を持ち、現在も中国で一番飲まれているのが、無発酵茶である緑茶です。緑茶は唐の時代に中国から日本に伝播され、現在では発酵の止め方などに違いがあります。
・中国緑茶: 香ばしく、お湯をつぎ足す毎に味わいが深くなる。茶葉を目で楽しむ。
・日本の緑茶: 新鮮味を重視し旨みが強い。抗酸化作用が高い。
中国緑茶の特徴を知ってから飲んだ方が、美味しいと感じました。ちなみにジャスミン茶などの花茶は、緑茶や白茶に花の香りをつけたものです。
○白茶

茶葉を揉み込まず、時間をかけて微発酵させて作られる白茶。生産が難しく、産地も福建省などに限られる希少価値の高いお茶です。アミノ酸、ポリフェノール、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれ、アレルギー改善効果もあります。
○黄茶
お茶好きが最後に辿り着くとも言われる、中国でもほとんど飲まれない稀少なお茶です。
○烏龍茶(青茶)

緑茶の爽やかさと紅茶の華やかさを併せ持った半発酵茶です。発酵度は銘柄によって幅広く、「鉄観音」「岩茶」などがあります。
今回購入した凍頂烏龍茶は、台湾南投県の標高1000メートル以上の山腹で栽培された発酵度が低い烏龍茶です。香り高く円やかな味わいで、昼食のあと一息つくのにぴったりでした。
○紅茶

紅茶の発祥は中国ですが、元々中国で飲む習慣はありませんでした。欧米向けの輸出目的で生産されていましたが、近年開発された新品種が国内人気の火付け役になったそうです。中国の紅茶は渋みが少なく、円やかな味わい。砂糖を入れずにストレートでいただきます。
私の場合最初は何か物足りなく感じましたが、飲んでいるうちに何杯も飲める優しい紅茶という印象に変わっていきました。
○黒茶
一般に流通している黒茶は、発酵させた「熟茶」です。雲南省のプーアル茶が有名で、薬のようなクセのある風味。ダイエット効果、胃痛・子宮系に良く、女性に嬉しいお茶でもあります。
大きめのカップに茶葉を入れお湯を注ぎ、さし湯をしながら10杯は美味しくいただけます。私たちの長いおうち時間、テレワークにぴったりのお茶なのです。(ただ実際は5杯目位で飽きます。)
おすすめの中国茶は?

「XINGCHA」のYuyinさんに、中国茶の選び方を聞いてみました。
・寒い季節、特に冷え性の人は、発酵度の高い温茶(黒茶や紅茶)を選ぶと温まる
・初夏や夏のティータイムには、緑茶や発酵度の低い台湾烏龍茶がおすすめ
イタリア料理との相性についてもアドバイスをもらいました!
・肉料理には消化を助ける岩茶(福建省産の烏龍茶)やプーアル茶
・魚料理を食べた後、口の中をスッキリさせたい時には白茶
・サラダなど軽いお料理には、紅茶や岩茶で涼と温のバランスをとる
・パスタにはどれも合うので、好きなお茶をチョイス

皆さんもお気に入りの中国茶を見つけて、ぜひ家のお茶レパートリーに加えてみてくださいね!

映像ディレクターなどを経験し、ヨーロッパなどを旅した後に、NYに留学。そこで出会ったイタリア人の旦那さんとの結婚を機にミラノに。現在は育児の傍ら、通訳や日本食ケータリングのお仕事もしています。人との距離感やテンション、センスなどミラノの全てが大好き! 記事では街やそこに住む人々の魅力も伝えていきたいです。様々な形で日本とイタリアの橋渡しができればと思っています!
この著者の記事一覧へ