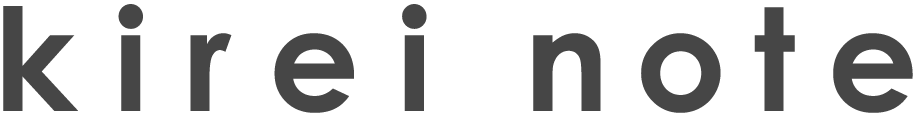ネムネムの季節に「ひじき」
ひじきのビビンバ
仕事を休むほどではないけど、体がだるい、気持ちがスッキリしない、“なんとなくの不調”ってありますよね。
それ実は、季節や気候の変化が影響しているのかも。「季節の症状の改善には季節の食材が効果的」という東洋医学の知恵に基づき、旬をおいしくとり入れた献立=食養膳をお届けします。カラダとココロをセルフメンテナンスしていきましょう!
3月前期のカラダとココロ
寒暖差が大きくなるこの時期は、気温の変化に対応するため交感神経が活発になり、いつの間にかカラダは緊張状態に。また、気圧の変化も激しいことで、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなり、自律神経が乱れやすくなります。 東洋医学の考え方「五行(ごぎょう)」では、心身に対する役割や機能を、肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)の5つに分類。これらは臓器とは違います。その中で、この季節にしっかり機能するべきなのが、自律神経の働きを調節する「肝」です。しかし、ストレスや疲労などの影響で「肝」の働きが悪くなることで、睡眠の問題が生じることに。上記の「肝」と、思考・精神をコントロールする「心」に血が足りない状態「血虚(けっきょ)」でも睡眠に影響が出てきます。
布団に入ると昼間あった嫌なことを思い出す、トラブルの解決策をあれこれと考え続ける、仕事のアイデアを思いついて考え始めてしまう、など、とにかくいろいろ思考が巡ってしまう。その結果、寝つきが悪い、朝早く目が覚めてしまう、朝から倦怠感があってだるいといった状態になります。寝ている間もリラックスできず緊張状態が続くため、眠りが浅くなることや、歯ぎしりのせいで朝起きたときから肩が凝っている場合も。 ぐっすりと深い睡眠をとって、元気に翌朝を迎えるためには、温かく栄養のあるものを食べること。また、少しでもリラックスできるように、シソやミント、ラベンダーやカモミールなどのハーブをとり入れることも大切です。
この季節になるべく避けたいこと
消化の悪い食べもの、熱になる食べもの(香辛料、こってりと甘いもの、もち米)、ストレス、パソコンやスマホなどによる目の酷使、不規則な生活、昼寝

ネムネムの季節に「ひじき」
あまり知られていませんが、ひじきは春が旬です。海藻のひとつであるひじきは、低カロリーで食物繊維が多く、ビタミンやミネラル、カルシウムも豊富で、栄養バランスに優れた食材。東洋医学では、肝と心の血を補って入眠しやすくする効果があるといわれているほか、肝に栄養を与えて働きを良くする作用も。睡眠の改善を助けるために、ぜひ食事にとり入れてみてください。ちなみに、漢方では「髪は血の余り」といわれていて、血を補うひじきは髪に栄養を与える役割も果たします。
ひじきを使った主菜
ひじきのビビンバ

材料(2人分)
- 乾燥ひじき 5g
- ごま油 小さじ1
- 砂糖 小さじ1/2
- しょうゆ 小さじ1
- コチュジャン 小さじ1/2
- 白ごま 少々
- 大豆もやし 100g
- ごま油 小さじ1
- 塩 少々
- にんにくすりおろし 少々
- 白ごま 少々
- 菜の花 50g
- ごま油 小さじ1
- 塩 少々
- 白ごま 少々
- にんじん 50g
- ごま油 小さじ1
- 塩 少々
- しょうゆ 小さじ1/2
- 白ごま 少々
- ごはん お茶碗2杯分
- 韓国のり 適宜
- 温泉卵 2個
和食の献立になりがちなひじきをコチュジャンでピリ辛に調理して、韓国料理・ビビンバのメイン具材にしました。通常はお肉を使うところをひじきでヘルシーにアレンジ。同じく旬の食材である菜の花も盛り込みました。ボリュームがしっかりあって、野菜をたっぷり食べられる、満足感の高い丼メニューです。ナムルは多めにつくっておけば、常備菜として冷蔵保管が可能。おかずとしてそのまま食べてもいいですが、韓国風のり巻き・キンパにするのもおすすめですよ。


心や体の状態によって食べたいものは変わります。わたしは元気がないときはチョコレートなどの甘いもの、イライラしているときはジャンクフードなど味の濃いものが食べたくなります。体が欲するものを少しだけとり入れたら、あとは体をいたわる食事に戻して、休養をとる。自分の状態に目を向けることが大事だと思います。
(献立担当) 鈴木聖子 Seiko Suzuki
料理研究家。大学で栄養学を習得し、卒業後は飲食店のスタッフトレーニングや商品開発の仕事に従事。その後オーストラリアへ渡り、レストランで働きながら食文化を学ぶ。帰国後はクッキングスクールに10年間勤務。2013年から「3さいからはじめる料理教室 KISSAKO」を主宰。季節の食材を使う料理レッスンのほか、企業向けのレシピ開発、ケータリング、加工食品販売なども手掛ける。頭の中は常においしいもののことでいっぱいな二児の母。
料理教室・料理研究家KISSAKO / instagram / facebook

眠りにくいときは、遮光カーテンやアイマスク、耳栓などを使用することをおすすめします。不安を煽るような情報をシャットダウンすることも大切です。
(カラダとココロ担当) 飛奈光重 Mitsue Tobina
漢方家。大学の薬学部在学中、医療ミスで祖母を亡くした経験から東洋医学と漢方の道へ。卒業後は漢方専門薬局に勤務し、数多くの漢方相談を受けることで臨床経験を積む。2019年「漢方専門 横浜梅桜堂薬局」を開業。婦人病、皮膚病、目の病気の研究に特に力を入れている。漢方歴25年、薬剤師と国際中医師の資格を持つ。
横浜梅桜堂薬局
編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。
この著者の記事一覧へ