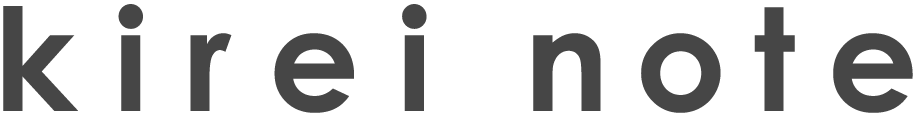バテバテの季節に「きゅうり」
きゅうりとエビの水餃子
仕事を休むほどではないけど、体がだるい、気持ちがスッキリしない、“なんとなくの不調”ってありますよね。
それ実は、季節や気候の変化が影響しているのかも。「季節の症状の改善には季節の食材が効果的」という東洋医学の知恵に基づき、旬をおいしくとり入れた献立=食養膳をお届けします。カラダとココロをセルフメンテナンスしていきましょう!
7月後期のカラダとココロ
この季節は、年に4回ある「土用(どよう)」のひとつ、「夏の土用」(2020年は7月19日~8月6日)です。よく耳にするのは鰻キャンペーンでおなじみの「土用の丑の日」ですが、これは古くから「夏の土用は、“う”のつく食べ物を食べると夏バテしない」といわれていることに起因しています。この時期は、急に体調を崩したり、妙にお腹がすいて食べすぎたりすることも。
土用の期間は、人間の根本的なエネルギーが弱まって疲れやすい状態に。東洋医学ではこれを「腎虚(じんきょ)」といいます。また、胃とその経絡に沿った炎症「胃熱(いねつ)」が起こり、胃の痛み、重さ、むかつき、咽の腫れ、肌荒れ、皮膚病の悪化、歯が浮くなどの症状も出やすくなります。あっさりした食事とたっぷりの睡眠を心がけて、この時期を乗り切りましょう。
この季節になるべく避けたいこと
辛いもの、脂っこいもの、こってりと甘いもの、寝不足

バテバテの季節にきゅうり
きゅうりは、夏の土用に食べると体にいいといわれている“う”のつく食材“ウリ科”の一種。胃の熱を冷まし、余分な水を排出してむくみをとり、必要な水分を補給してくれる作用があります。胃腸を冷やしすぎないために、加熱調理がおすすめ。
きゅうりを使った主食
きゅうりとエビの水餃子
材料(2人分)
- きゅうり 1本
- むきエビ 80g
- 鶏ひき肉 80g
- (つなぎになります。豚ひき肉でもOK)
- ☆塩小さじ1/2
- ☆酒小さじ2
- ☆しょうゆ小さじ2
- ☆片栗粉小さじ2
- 餃子の皮 12枚
梅雨明け後の痺れるような暑さ、屋外とエアコンが効いた室内との気温差、そんな中でバテバテになるこの季節は、さっぱりとしたものが食べたい気分。今回のテーマ食材「きゅうり」は、サラダや漬物など生で食べるイメージですが、加熱してもとても美味しくいただけるんです。そこで、ぷりぷりのエビと鶏ひき肉を合わせて、ツルンと喉ごしのいい水餃子にしました。あっさりしつつ、存在感とボリュームもバッチリ。お好みでポン酢や酢醤油をつけてめしあがれ。


いつも同じ食材を買っていると、自然と同じ料理を作ってしまいます。
マンネリを感じたときは、買ったことがない食材や調味料に手を出してみましょう。
(献立担当) 鈴木聖子 Seiko Suzuki
料理研究家。大学で栄養学を習得し、卒業後は飲食店のスタッフトレーニングや商品開発の仕事に従事。その後オーストラリアへ渡り、レストランで働きながら食文化を学ぶ。帰国後はクッキングスクールに10年間勤務。2013年から「3さいからはじめる料理教室 KISSAKO」を主宰。季節の食材を使う料理レッスンのほか、企業向けのレシピ開発、ケータリング、加工食品販売なども手掛ける。頭の中は常においしいもののことでいっぱいな二児の母。
料理教室・料理研究家KISSAKO / instagram / facebook

疲れやすくなる夏の土用期間は、絶対に寝不足しないこと。
いつもより1時間ほど多く睡眠をとるように意識することが大切です。
(カラダとココロ担当) 飛奈光重 Mitsue Tobina
漢方家。大学の薬学部在学中、医療ミスで祖母を亡くした経験から東洋医学と漢方の道へ。卒業後は漢方専門薬局に勤務し、数多くの漢方相談を受けることで臨床経験を積む。2019年「漢方専門 横浜梅桜堂薬局」を開業。婦人病、皮膚病、目の病気の研究に特に力を入れている。漢方歴25年、薬剤師と国際中医師の資格を持つ。
横浜梅桜堂薬局
編集部のおすすめやお知らせをアップしていきます。
この著者の記事一覧へ